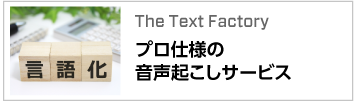“良いインタビュー”の定義


“良いインタビュー”とは何か。まさに哲学的な、というか、禅問答のような、というか、大きなふわっとしたテーマではありますが、私の持論を展開させていただきます。
私はどちらかというと実利的な人間です。理想論や空論を語っているだけでは食っていけないので、自分が持ってるインタビュースキルを、いかにマネタイズしていくかを考え続けております。自慢するわけではないですが、おかげさまで私は、インタビューで食っています。インタビューで食うためにはどうしたらいいかというと、やはりご愛顧いただき続けることであったり、リピートしていただくことだと思っています。すなわち、支持をされ続けるということが、良いインタビューをしている証だと思うので、良いインタビューができているからリピートをしていただいていると自覚しています。
もっといえば、リピートだけではなく、一度、私のインタビューを受けた方が、他のお客様を紹介してくださったりします。例えば、あるお客様の依頼を受けて、ある人にインタビューをするとします。仮にAさんから依頼を受けて、Bさんにインタビューをするとしたら、Bさんは私のインタビューを受けて満足してくれて、今度はBさんがお客様になって「うちの仕事もやってくれないか」と呼んでくれるようになったりします。
さらにBさんがCさんを紹介してくれるなど、紹介の輪がどんどん広がっていきました。こういうことが続いたときにはじめて、“私のインタビューは評価されているんだな”“ご満足いただいているんだな”と実感しました。良いインタビューをやってきたから、16年間食い続けていられるのかなと思っています。
では、改めて“良いインタビューって何だろう?”という話になります。ずばり“誰かがお金を払う価値を認めてくださっている”からこそ、リピートしてくれているということですよね。大前提として“人が喜んでくれる”ってことが一番大切です。お金を払ってでも感じたいと思えるくらいの喜びがあったということです。では、一体、誰を喜ばせばいいのか?
インタビューの現場には、いろいろな立場の関係者がいます。もちろん、自分の目の前のインタビューを受けてくださる人が喜んでくれることが一番なのですが、事例紹介とか、ユーザーインタビューなど一般的なインタビューワークでは、お金を払っているのは必ずしも目の前の人ではないケースの方が往々にしてあります。すなわち、現場にいるすべての関係者が満足しなければいけないのです。その中の誰かがひとりでも、私のことを「アイツはアカンやろ」と言い出したら、恐らく次はありません。それくらいシビアな現場です。
10年くらい前の話ですが、駆け出しからちょっとベテランになりかけくらいのときに、タレントの小堺一機さんにインタビューする機会をいただいたんですね。ちょうど小堺さんが大病を患って、それを克服したタイミングだったんですかね。日経新聞の広告のインタビューの仕事だったのですが、発注元は、日本医師会ですね。医師会くらいになると、やっぱり大手広告代理店に頼むわけですよ。そのときは博報堂さんだったのですが、私は80年代に青春を過ごした人間で、そういう時代に生きていると、広告代理店って雲の上のような存在なんですね。そのときに初めて一緒の現場になって、“生の博報堂だ”なんて思ったりしたんですよ。
それ以外に、日経新聞の担当者さんと日経の記事広告をまとめている広告代理店の人もいて、そして私のクライアントは制作会社で、その方もいる。医薬品とか健康食品の広告を専門にやっている制作会社で、それらの方々が現場にずらーっといるわけですよ。会場に入ったときに、こんなにいるのか!と思ったんですが、そりゃそうだろうなと。そういう方々が、私がインタビューをする背後に、ずら~~っと並ぶわけですよ。“コイツ、ヘマしないだろうな?”という目で、ずっと見ているわけですから、ものすごいプレッシャーがかったりするわけです。
でも私はそのときにビビることなく、“なんか面白いな”と思ったわけですね。すごい人数の関係者がいて、小堺一機さんのような大物のインタビューをするわけですよね。そんなすごい場なのに、私のような末端の人間が先頭に立って戦うわけではないですか。何だこの構図は?と思いながら、一生懸命やらせていただきました。みんなヒリヒリするわけですよ、失敗したらまずいわけです。小堺さんはものすごくいい人で全然問題はないんですが、著名人の中には若干、難しい人もいたりします。もしも私が変な質問をしてしまったら大変なんです。さらにいえば芸能人取材は与えられる時間が極めて限定されがちなので、その尺の中で必ず過不足なく全部聞かなくちゃいけない。そういうものを全部背負って、「アイツ大丈夫か?」って、みんなヒリヒリしているわけです。
皆さん、現場で初めて私に会ったわけですから、「伊藤秋廣って誰だ?知らないな」という目でみんなが見ているなかでインタビューをするわけですが、小堺さんを喜ばすと、多分、その現場が丸く収まるなと思ったんです。確かに小堺さんはすごく喜んでくれましたけどね。だから現場では、私が話を聞く相手を喜ばせたり、気持ちよくしゃべってもらったり、そういうことをしなくてはいけないんだなと思ったんです。しっかり結果を出して、“この人に頼むと安定しているな”とか、“ちゃんとやってくれるな”という安心感を与えることが大事なんだなって思いました。
言うなれば、書くものって何とでもなるだろうって思うのですね。本当はこんなことをカミングアウトしてはいけないのでしょうが、私は常に、私が書いているものがめちゃくちゃ評価されているなんて、全然思っていないんですよ。私なんかよりもレベルの高い人もいるし、きっちり書く人もいる。だけど、現場が台無しだったら最悪だと思うのですよ、取り返しがつかないから。書く行為は、あとで取り返しがつくのですよ。
全部が全部ではないですが、自分が出した初稿が、いろんな関係者の手に渡って赤が入って、ブラッシュアップされていくではないですか。それでいいと思うのですね。だけど私はこの瞬間、生の本番で与えられた時間の中で、誰もが満足するベストパフォーマンスのインタビューをしますよと、そこには絶対的な自信があります。自信があるインタビューをきっちりやらなくてはいけないと、意識を高めて仕事に向かっているわけですが、その姿勢を周りの方が認めてくださっていて、「伊藤に現場を任せれば間違いないよね、どんな難しい相手でも、話を引っ張ってくれるよね」という安心感につながり、それがリピートに繋がっているのだろうなと思っています。
本番の強さって何かといえば、これを言ったら元も子もないのですが、結局は経験なんですよ。ただ経験しただけではなくて、その経験を記憶することです。インタビューって30分とか45分の中で細かく小さな判断を、たくさんする必要があるのですよ。こんな局面でどんな処理をしてきたか、相手がちょっと不機嫌になってきた時はどうするかなど、相手の表情を見ることもそうですし、相手の反応を見てこういう返事をしようとか、それは確かに経験ですが、経験しているだけでは対処ができないんです。経験したことをちゃんと記憶しておいて、こういうケースの時にはこんな話をしようとか、こういう風に持っていこうとか、それを瞬時に引き出しから取り出していく必要があります。
この間、Netflixで「クイーンズ・ギャンビット」というドラマを見たんです。チェスのドラマなんですけれども、ご存じですか?チェスの名手は何が優れているかというと、やはり同じことを言っていて、経験と記憶なんだそうです。チェスの駒を動かした時に、前は相手がこんな手を打ってきた、そのケースを瞬時に出していくことが重要という話があって、インタビューとチェスに共通点があるなと思ったんです。
さらに以前にジャズミュージシャンにインタビューしたことがあって、その時も同じようなことを聞いたんです。ジャズのアドリブってありますよね、あれは最初にテーマがあって、そこからアドリブに入り、最後にテーマに戻る。どうやったらこんなにアドリブを構成していけるのかというと、決して適当に吹いているわけではないんですよね。瞬時にひらめいたり、毎回違うことをやるんですかと質問したら、そのジャズミュージシャンの方は、過去の優れたアドリブのフレーズを、とにかく自分なりに焼き直すという話をされていました。大好きなアーティストの演奏をたくさん聞いて、さまざまなアドリブを常に自分のなかに入れているんだそうです。優れたミュージシャンとは、過去のミュージシャンにリスペクトして、その美しいフレーズを持ってくるということが多いと聞いて、なるほどと思いました。
アドリブやとっさの判断のように見えて、実は自分が過去にやってきたことをその場で再現しているという部分では、インタビューとチェスとジャズに共通点があると思ったのです。