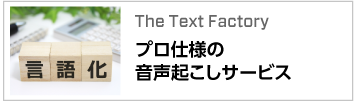【BEST INTERVIEWS】映画監督・谷内田彰久さん


ドラマ的嘘や映画的嘘のないものを描く
谷内田彰久氏は、自らの仕事を“一般的な映画監督業とはかけ離れている”と説明する。作品作りに関わる実務はもちろん、それ以外にプランナー、プロデューサーなど多様な側面を持ち、各種プロモーションからタイアップの仕掛けづくりまで、クリエイティブ、ビジネス領域の境なく縦横無尽に動き回っている。
恐らく、日本の映画界、いや映像の世界全般において、このような立ち位置にある人は他には存在しないであろう。そのマルチな才能の源泉は、谷内田氏のユニークな経歴にある。
「学生時代には演劇をやっていたのですが、役者ではなく現実味のある演出家の道を選びました。TV業界に就職して、24歳ではじめて深夜枠のドラマを手掛けて監督デビュー。その年に独立を果たし、CMからドラマまで年間200本近い作品の制作に携わってきました。もう、そうなると、ほぼ毎日、何かを作っているような状態ですよね」
ところが27歳になったある日、人に演出をつけることに限界を感じはじめたとのだという。
「結局、自分が経験していないことを演出するというのは想像の範疇でしかなかったから、圧倒的に経験が足りない。“もう思いつかない”とプロデュース側の人間に回ろうと考えたのです」
CM製作で繋がりのあった企業とのコネクションを活かしながら、映像制作のみならず、ライセンスビジネスにも着手。面白そうな案件に次々と投資を繰り返しながら、自らが立ち上げた会社は急成長を果たしていったのだという。
「ところが30歳を目前にして会社の業績が急落。ほぼ無一文になった状態で、半分逃げるようにして韓国へと移り住みました。そこで結婚して、しばらくおとなしく暮らしていたのですが、生活のために働かなくてはなりません。向こうで議員の秘書をしたり、韓国製のカラーコンタクトを日本で販売するECサイトを運営したり、韓国産のアサリを卸したりと様々なビジネスを少しずつ展開するようになりました」
やがて日本相手のビジネスのウエイトが大きくなり、東京にも頻繁に訪れるようになったという谷内田氏。そこで運命的な出会いが起こる。
「それを見て自分が監督になろうと決めた作品を制作したプロデューサーと偶然にもお会いする機会があったのです。それと同時に、私の会社でシステムを作っていた社員が持ってきた小説が面白くて、これを映画化できないだろうか?という思いがふつふつとわいてきたのですね。企画段階でまたストーリーを作る面白さに引き戻されたのです」
様々な経験を重ねて、再び映像の世界へ舞い戻ってきた谷内田氏。しかし、自らの仕事は一貫して変わらなかったと語る。
「私の肩書はどの時代も演出家ですよ。どうすれば利益を上げることができるか、どうすれば集客できるかを考え、そのために仕掛けをしたり、あらゆる手を打っていく。CMやドラマのプランを考えるのとなんら変わりがないと思っています」
とはいえ、この一連のビジネス経験が谷内田氏の演出にさらなる深みを与えるようになったのは間違いなかろう。
「演出が生々しくなったと思います。結構、人生のどん底まで落ちていって、ひどい目にもあってきましたからね(笑)。世の中のリアルってこういうものだとわかっていますから、ドラマ的嘘や映画的嘘のないものを描きたいと思うのです」
映画『ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど。』に続き、人気コミックアプリcomicoの実写映画「爪先の宇宙」の制作にも着手。しばらくは映像の世界で生きていこうと考えているという。
「そこに生きた人間を作らなくてはいけない仕事です。私はあらゆる社会経験を重ねてきたから、その空気感を人に伝えることができる。今は、それが面白くて仕方がないのです」
2016年10月インタビュー