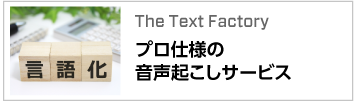【東京国際映画祭関連】物語の構造はラブコメディ。お節介パワーで千夏にエールを送る


東京国際映画祭出展作品『あつい胸さわぎ』まつむらしんご監督へのインタビューです。
――この作品を映画化に至った思いをお聞かせください。
「演劇ユニットiaku」という劇団が、3年前に小劇場の演目として『あつい胸さわぎ』を上演していました。僕はそれまで「iaku」のことを全く知らなかったのですが、友人から「多分まつむらくんに合うよ」とすすめられたんです。それで、何の気なしに見に行ったんです。
そしたら舞台があまりにもよくて。上演中から「これを映画にしたい」とすでに思っていました。帰りの電車の中では「絶対に映画にしよう」と決意していて、すぐに原作者の横山拓也さんに僕自身がメールをしました。そこから横山さんとお会いする機会をいただいて「映画化させてください」とお願いしました。
――映画化したいと強く思ったのはなぜですか?
今回が監督として長編3本目で、過去2作はラブコメディでした。大学院でもラブコメを研究していて、もともとラブコメ作家になりたかったんです。『あつい胸さわぎ』は、若年性乳がんがテーマになっていますが、物語の構造自体はラブコメに近く、男と女の三角関係という話でもあるので、これは僕の好きな物語のフォーマットだなと思いました。それに親子の話でもあり、自分の実体験もあるし、以前作った自主映画が親子の葛藤を描いたものだったので、そこも重なるなと思いました。
もうひとつは、ひとりの完全にお節介なおじさんというか……。命には直接かかわりはないけれど、主人公の千夏が胸を失うという題材を見たときに、お節介だけれど「君の人生はまだ大丈夫だよ」とエールを送りたかった。完全なるお節介パワーなんです(笑)
舞台では、はっきりとポジティブな終わり方をしていないので、映画ではそのエールの部分を強く表現したいと思ったんです。
――映画を撮影するうえでチームづくりなど心がけたことはありますか?
映画監督はカリスマか、裸の王様か、2パターンしかいないと思っています(笑) 圧倒的なカリスマ性があってグイグイ引っ張っていくタイプか、もうこいつはダメだから我々が頑張らないと良いものにならないからとスタッフが奮起してくれるかの2パターンということです。
僕は圧倒的にカリスマ性がないので(笑) スタッフやキャストに、「こういう思いで作っていきたい」とだけ伝え、技術やセンスなどみなさんの能力をお貸しくださいと訴えました。多分みんな「しょうがないね」と思いながら頑張ってくれたんじゃないかな。
――映画をご覧になる方に、こう見てほしいという思いはありますか?
どう見てほしいというのは正直ないです。けれど、こうは見られたくないというのは明確にあります。病気を苦にした女の子のいわゆる“病気もの”的な、見ている人の涙を誘うものにだけはしたくないと思っています。あくまでも彼女の青春期の恋愛そして失恋、親との葛藤に初期の乳がんを並列にしたかった。
もしかしたら、乳がんサバイバーの方からひんしゅくを買うような意見かもしれませんが、ひとつの親子の物語、ひとつの青春映画、ひとつの恋愛映画として見てほしいと強く願っています。胸を失うことはひとつの障害でありテーマではありますが、それがなくてもこの物語は成立すると思っていますから。
――病気に支配されない千夏のあり方がリアルで切なく感じたのは、監督のそうした意図があったからなんですね。
多分そういうところは監督が持っている性格が反映されると僕は思っています。タッチは技術者も関わるから、微妙に変えられるものなんですが、自分の性格は簡単に変えられないですから。
僕は不幸な話に興味がないんです。だってみんな不幸になるから。この先、社会が良くなるとは全く思っていなくて、「絶望しか待っていない」という思いが常に頭にあるんです。だから、絶望を描いてもしょうがないと思っていて。お金を払って映画館のスクリーンで2時間もかけて見るものは、超リアルに描いているように見えて、超フィクションを描いているものだと僕は思っています。
――見終わったとき、誰もが明るい気持ちになっていると思います。
この映画の脚本はラストシーンから決めていて、舞台にはない映画のオリジナルなんです。舞台は、お母さんの昭子が千夏を後ろから抱きしめるところで終わるので、ちょっと閉じた印象がありました。僕としては、あの先を感じられなかったという思いがあって。消化不良だった部分を自分で消化したいという思いはありました。
脚本をお願いした髙橋泉さんから「まつむらくんはこの映画をどこに向かって作りたいの?」と聞かれて、先ほどのように「絶望には興味がない。彼女が前を向いて生きていけるようにしたい」と伝えたんです。そうしたら「わかった、それなら書けるよ」と言ってラストシーンを書いてくれました。最初に脚本を読んだとき、うまいなって思いました。自分が書くよりも彼が書いた方が絶対にいいと思ってはいましたが、あのラストが来たときに改めて正解だったと思いましたね。
――まつむら監督が、映画づくりでこだわりたいところを教えてください。
映画はものすごいお金がかかりますし、ものすごい数の人が関わっているから、商品としてちゃんと成立させたいという思いがあります。僕の個人制作ではないので、そういう意味でもちゃんと商品性、商業性は考えたいです。
『あつい胸さわぎ』の舞台は再演も含めて、最大で2,000人から3,000人しか見ることができない。映画はどれだけ興行に失敗したとしても、3万人くらいには見ていただけるわけで、舞台とはやっぱり規模が違う。それに舞台は5,000円も6,000円も払うから基本的に好きな人しか行かないけれど、映画はもっと気楽ですよね。映画館でも2000円ほどで見られるし、配信だったらボタンを1個押せば流れる。そういう意味でも商業性をちゃんと持ちたい。
もともと映画を始めた理由は「何かを訴えたい」「何かを語りたい」という作家性の部分が大きくあって志しているので、そこを捨てずに、なおかつ社会で流通させるというのを両立したいんです。まだそこまではなっていないですけれど(笑) 僕は自分の半径5mの世界を描きたいと思っているんです。届く先が半径5mではダメなんですけれど。これはいつも思っていることです。
――東京国際映画祭で上映されることについて、どのように受け止めていらっしゃいますか?
正直ホッとしているというか。実は僕が監督をしたこれまでの作品も、釜山国際映画祭や上海国際映画祭で上映されているので。嬉しいというかホッとしています、最低限の仕事を果たせたという認識です。
映画は商業性がないと映画館で上映できない。でもそういうもの以外にも、いろんな作品があることを広く知らしめるのが映画祭の目的のひとつだと思うんです。だから、商業性のあるものはお金払って見に行けばいいので省かれる場なんです。
僕がつくりたい映画は商業性や作家性、社会性をうまく混ぜたいから、実は一番中途半端。作家性だけに特化すればもっと映画祭に行けるし、商業性だけに特化すればもっと広く売れるというのは分かっているんです。けれど僕がやりたいのは、それらをハイブリッドしたものであり、どちらかだけではダメなんです。自分の中でも理想としているところに行き着いている訳ではなくて、まだまだ弱いと思っているんです。ただそう思いながらも、映画祭に入れていただけると、少しは認められているのかなと安心できますね。